◎形から入って自然に整う
能阿弥は、室町時代の人で、もと越前朝倉家の被官であったが、将軍足利義教、義政に同朋衆として仕えて、茶道の様式を最初に整理した人物となった。以下の引用文を見ると、茶道の作法、ファッション、様式が、寄木細工というか、当時の様々な技芸、流行のコラボであったことが窺われる。よく映画やドラマで取り上げられる茶杓の置き方を見ると、その所作に何か見覚えがあると思い出されるが、矢の扱い方であったとは面白い。能の歩き方まで入っている。
茶の作法の個々の意義づけや由来はともかくとして、「形から入って自然に整ってくる」という狙いこそは、その定めた様式を自然に体現する人物の出現を何百年でも待つというオーソドックス系宗教(顕教系)の哲学と共通している。
パドマ・アーサナも、その心境がとある状況になれば、その坐相となり、パドマ・アーサナが起こる。
『能阿弥は、義教の死後、八代将軍義政に仕えた。彼が、書院飾や台子飾の法式を一応完成したのは、恐らくこの東山時代のことと思われる。台子の飾り方が規定されると同時に、茶器の扱い方、置合せの寸法なども自然ときまってくる。
置合せの寸法を曲尺割(かねわり)というが、これは、利休の師匠の武野紹鷗が規定したともいうが、能阿弥に始まるという説もある。恐らく、能阿弥が創め、紹鷗に至って完成されたのであろう。
それから、点茶の方式も、闘茶では禅院の点茶法を真似ていたが、能阿弥は、小笠原流の礼法を参酌して、今日行われているような茶の点て力を考案した。
風炉の茶事の柄杓(ひしゃく)の扱い方に、置き柄杓、切り柄杓、引き柄杓と称する三通りの動作があるが、これは、弓の矢の操法からきている。小笠原流が採り容れられた証拠であろう。
また、点茶の際の動作、特に道具を運ぶ際の歩き方などは、能の仕舞いとそっくりである。これは、能の所作を茶道に採用した一例と思われる。
点茶の際の服装も、前に述べた唐様の闘茶会における主客の姿と違って、和様化されただけでなく、書院の茶法では、厳粛な礼装をした。「南坊録」によれば、赤松貞村は、後花園天皇に献茶した際に烏帽子と水干であったが、義政は狩衣を着したという。
また、たとい稽古の際でも、俗人は裃(かみしも)、僧体の者は袈裟十徳、貴人は素袍(すおう)という定めであった、と記している。素袍は、利休の活躍した安土桃山時代には武人の礼装であって、下に素袍袴(すおうばかま)をはくが、義教や義政の頃は下級武士の服装であり、上流の武士は公家と同様に狩衣(かりぎぬ)を礼服としたので、義政も台子の点茶には狩衣を着用したのであった。狩衣の場合は、烏帽子をかぶり、指貫(さしぬき)を用いる。
こうなってくると、少なくとも上流武家の社会では、将軍家の影響を受けて、礼儀正しい茶湯が勢力を占めてくる。道具の飾り方とか、点茶法とか、服装とかいう外形的なことだけでなく、心の礼も、形から入って自然に整ってくる。
殊更に約束の時刻をたがえたり、茶席で大酒をしたり、博打をすることは勿論、本非の勝敗を争うというようなことも二の次となり、闘茶遊芸は自然消滅の状態となる。茶道への第二歩は、確かに茶礼の成立であり、その貢献者の主なものは義政の同朋能阿弥だったと云える。
珠光流茶道の秘伝書「山上宗二記」によると、能阿弥は向朋衆の中の名人であったという。この場合、名人とは、茶湯の名人のことである。茶湯の名人とは、唐物道具を所持し、目利きも茶湯も上手で、作意も手柄もあり、しかも一道に志の深い者を云い、そのうち歴史上にその名を遺す程の者を特に古今の名人と称し、利休以前の例として、珠光・引拙・紹鷗の三人を挙げている。』
(世阿弥と利休/桑田忠親/至文堂P136-138から引用)
※本非:茶の飲み比べで、最初は栂尾の茶を本、宇治茶を非としていたが、時代が下がると本非が逆になった。
※闘茶:茶の飲み分けで、賞品として、結構な金子、褒美を争った。
![]() 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
![にほんブログ村 哲学・思想ブログ スピリチュアル・精神世界へ]() にほんブログ村
にほんブログ村
【ザ・ジャンプ・アウト】 【悟りとは何か】 【ダンテス・ダイジ】 【クリシュナムルティ】 【OSHOバグワン】 【出口王仁三郎】 【道元】
【生の側から窮める】 【死の側から窮める】 【通俗人間性からのジャンプ】
【肉体】 【エーテル体】 【アストラル体】 【メンタル体】 【コーザル体】 【アートマン】 【ニルヴァーナ】
【アトランティス】 【現代文明】 【日本の行く末】
能阿弥は、室町時代の人で、もと越前朝倉家の被官であったが、将軍足利義教、義政に同朋衆として仕えて、茶道の様式を最初に整理した人物となった。以下の引用文を見ると、茶道の作法、ファッション、様式が、寄木細工というか、当時の様々な技芸、流行のコラボであったことが窺われる。よく映画やドラマで取り上げられる茶杓の置き方を見ると、その所作に何か見覚えがあると思い出されるが、矢の扱い方であったとは面白い。能の歩き方まで入っている。
茶の作法の個々の意義づけや由来はともかくとして、「形から入って自然に整ってくる」という狙いこそは、その定めた様式を自然に体現する人物の出現を何百年でも待つというオーソドックス系宗教(顕教系)の哲学と共通している。
パドマ・アーサナも、その心境がとある状況になれば、その坐相となり、パドマ・アーサナが起こる。
『能阿弥は、義教の死後、八代将軍義政に仕えた。彼が、書院飾や台子飾の法式を一応完成したのは、恐らくこの東山時代のことと思われる。台子の飾り方が規定されると同時に、茶器の扱い方、置合せの寸法なども自然ときまってくる。
置合せの寸法を曲尺割(かねわり)というが、これは、利休の師匠の武野紹鷗が規定したともいうが、能阿弥に始まるという説もある。恐らく、能阿弥が創め、紹鷗に至って完成されたのであろう。
それから、点茶の方式も、闘茶では禅院の点茶法を真似ていたが、能阿弥は、小笠原流の礼法を参酌して、今日行われているような茶の点て力を考案した。
風炉の茶事の柄杓(ひしゃく)の扱い方に、置き柄杓、切り柄杓、引き柄杓と称する三通りの動作があるが、これは、弓の矢の操法からきている。小笠原流が採り容れられた証拠であろう。
また、点茶の際の動作、特に道具を運ぶ際の歩き方などは、能の仕舞いとそっくりである。これは、能の所作を茶道に採用した一例と思われる。
点茶の際の服装も、前に述べた唐様の闘茶会における主客の姿と違って、和様化されただけでなく、書院の茶法では、厳粛な礼装をした。「南坊録」によれば、赤松貞村は、後花園天皇に献茶した際に烏帽子と水干であったが、義政は狩衣を着したという。
また、たとい稽古の際でも、俗人は裃(かみしも)、僧体の者は袈裟十徳、貴人は素袍(すおう)という定めであった、と記している。素袍は、利休の活躍した安土桃山時代には武人の礼装であって、下に素袍袴(すおうばかま)をはくが、義教や義政の頃は下級武士の服装であり、上流の武士は公家と同様に狩衣(かりぎぬ)を礼服としたので、義政も台子の点茶には狩衣を着用したのであった。狩衣の場合は、烏帽子をかぶり、指貫(さしぬき)を用いる。
こうなってくると、少なくとも上流武家の社会では、将軍家の影響を受けて、礼儀正しい茶湯が勢力を占めてくる。道具の飾り方とか、点茶法とか、服装とかいう外形的なことだけでなく、心の礼も、形から入って自然に整ってくる。
殊更に約束の時刻をたがえたり、茶席で大酒をしたり、博打をすることは勿論、本非の勝敗を争うというようなことも二の次となり、闘茶遊芸は自然消滅の状態となる。茶道への第二歩は、確かに茶礼の成立であり、その貢献者の主なものは義政の同朋能阿弥だったと云える。
珠光流茶道の秘伝書「山上宗二記」によると、能阿弥は向朋衆の中の名人であったという。この場合、名人とは、茶湯の名人のことである。茶湯の名人とは、唐物道具を所持し、目利きも茶湯も上手で、作意も手柄もあり、しかも一道に志の深い者を云い、そのうち歴史上にその名を遺す程の者を特に古今の名人と称し、利休以前の例として、珠光・引拙・紹鷗の三人を挙げている。』
(世阿弥と利休/桑田忠親/至文堂P136-138から引用)
※本非:茶の飲み比べで、最初は栂尾の茶を本、宇治茶を非としていたが、時代が下がると本非が逆になった。
※闘茶:茶の飲み分けで、賞品として、結構な金子、褒美を争った。
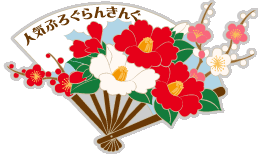 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ にほんブログ村
にほんブログ村【ザ・ジャンプ・アウト】 【悟りとは何か】 【ダンテス・ダイジ】 【クリシュナムルティ】 【OSHOバグワン】 【出口王仁三郎】 【道元】
【生の側から窮める】 【死の側から窮める】 【通俗人間性からのジャンプ】
【肉体】 【エーテル体】 【アストラル体】 【メンタル体】 【コーザル体】 【アートマン】 【ニルヴァーナ】
【アトランティス】 【現代文明】 【日本の行く末】
